エンジン分解図
 大まかなエンジンの分解図です。プラスドライバー(#1、#2)と6角レンチさえあれば簡単に分解できます。本体、リコイルスターター、マフラー、キャブレターの構成です。
大まかなエンジンの分解図です。プラスドライバー(#1、#2)と6角レンチさえあれば簡単に分解できます。本体、リコイルスターター、マフラー、キャブレターの構成です。
 エンジンの本体の分解図です。本当は本体のクランクシャフトが通る部分にボールベアリングが圧入さえているのですが外せませんでした。また回転軸(クランクシャフト)は本当は逆側から組み入れるのですが、わかりやすくするために前に配置しました。
エンジンの本体の分解図です。本当は本体のクランクシャフトが通る部分にボールベアリングが圧入さえているのですが外せませんでした。また回転軸(クランクシャフト)は本当は逆側から組み入れるのですが、わかりやすくするために前に配置しました。




 エンジン本体のブロックです。鋳鉄製で実際に近くで見ると表面は少々粗いですが一応エンジンマウントと燃焼室は綺麗に表面加工がされています。右上の写真が燃焼室(シリンダーがおさまる部分)です。左中の写真がエンジンブロックに圧入されているボールベアリングです。クランクケース側にも圧入されています。(右中の写真)左下の写真が排気ポートです。この先にマフラーを取り付けるために綺麗にフライス加工で縁取りさせていますます。
エンジン本体のブロックです。鋳鉄製で実際に近くで見ると表面は少々粗いですが一応エンジンマウントと燃焼室は綺麗に表面加工がされています。右上の写真が燃焼室(シリンダーがおさまる部分)です。左中の写真がエンジンブロックに圧入されているボールベアリングです。クランクケース側にも圧入されています。(右中の写真)左下の写真が排気ポートです。この先にマフラーを取り付けるために綺麗にフライス加工で縁取りさせていますます。


クランクシャフトは吸気弁兼ねた構造になっています。このシャフトの角度によって吸気孔が閉じたり開いたりして4サイクルエンジンの吸気弁の役割を果たしています。混合気はこのシャフトの切り欠きから入って、シャフトの後ろの穴からクランク室に入って行きます。


ピストンです。アルミ合金で出来ていて非常に軽いです。この部品は毎分20,000往復するだけあって、エンジンの振動・騒音、エンジンの最高回転数決め手と言っても過言ではないと思います。また4サイクルエンジンとの大きな違いはピストンリングが無いのと、側面に穴あ開いていることでしょう。この穴を通ってクランク室で1次圧縮された混合気は燃焼室に流れ込みます。

 コンロッドです。
コンロッドです。


シリンダーです。これもピストンと同じく側面に穴があり、1次圧縮された混合気ここを通って燃焼室に入り、爆発後の排気ガスの出口となります。2サイクルエンジンはピストンが上下することによってシリンダーの穴を塞いだり開けたりして4サイクルエンジンのバルブと同じ役割を果たしています。
 ヘッドです。燃焼室の天井でありというのもあってエンジンでもっとも熱く部分なのでヒートシンクみたいに放熱性が良い構造になっています。この上にちょうどプラグがささります。
ヘッドです。燃焼室の天井でありというのもあってエンジンでもっとも熱く部分なのでヒートシンクみたいに放熱性が良い構造になっています。この上にちょうどプラグがささります。


点火プラグです。ラジコン用に作られているので強烈な電気火花による「スパークノイズ」でRC装置(無線装置)が暴走を起こさないように電熱線で点火するようになっています。エンジンの始動後電気を止めてもは燃焼室で起こる「爆発」による熱をこの電熱線が次の爆発まで蓄えてそしてまた次の爆発まで蓄えて…と、連鎖してエンジンだけで回転します。エンジンを停止させるには燃料か吸気を断ちます。


 クランクケースのふたの部分です。円筒上に出ぱっている方がクランクケース側です。外周の4つのビス穴はリコイルスターターを止める部分で、内側がエンジン本体とこの部品を止めておくためのねじ穴です。右下がガスケットです。
クランクケースのふたの部分です。円筒上に出ぱっている方がクランクケース側です。外周の4つのビス穴はリコイルスターターを止める部分で、内側がエンジン本体とこの部品を止めておくためのねじ穴です。右下がガスケットです。

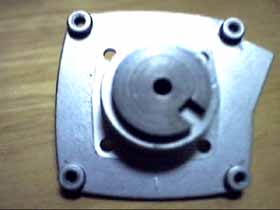




リコイルスターターの構造です。スターターのシャフトはクランク軸に掛かるようになって、スターターを引くとスターターの6角の穴にはまったワンウェイベアリングがスターターのシャフトを回し、エンジンが掛かると空回りするようになっています。スターター本体はプラスチックで出来ていますが、クランクケースは思ったよりも熱くならないので融けてしまうことはありません。もちろん触れば火傷をするのには十分な温度ですが…。




 マフラーの分解図と格部品の詳細です。このエンジンのマフラーは1室構造ですが中、上位モデルは2室構造になっています。長いねじはマフラーの排気管側とエンジンに固定する側を止めるネジで、ちょうど中心を貫通する形になります。排気管の他にある小さな管は排気ガスの圧力を利用して燃料をくみ上げるためにあるもので(バックプレッシャー)、ここと燃料タンクをつなぎます。排気ガスの温度はあまり高くならないので、良く冷却さえしていれば稼動中触っても火傷しませんでした。 決して試さないでください(笑
マフラーの分解図と格部品の詳細です。このエンジンのマフラーは1室構造ですが中、上位モデルは2室構造になっています。長いねじはマフラーの排気管側とエンジンに固定する側を止めるネジで、ちょうど中心を貫通する形になります。排気管の他にある小さな管は排気ガスの圧力を利用して燃料をくみ上げるためにあるもので(バックプレッシャー)、ここと燃料タンクをつなぎます。排気ガスの温度はあまり高くならないので、良く冷却さえしていれば稼動中触っても火傷しませんでした。 決して試さないでください(笑








キャブレター(気化器)です。混合気の濃さ(空燃比)とアイドリング(バルブの開閉範囲)の調節はここでしますので、ここの調整一つで出力と安定性と始動性に大きく影響を及ぼし、燃料の成分によっても微調整をしなくてはいけないが故に初心者の人はここの調節で悩んでしまいます。
戻る
 大まかなエンジンの分解図です。プラスドライバー(#1、#2)と6角レンチさえあれば簡単に分解できます。本体、リコイルスターター、マフラー、キャブレターの構成です。
大まかなエンジンの分解図です。プラスドライバー(#1、#2)と6角レンチさえあれば簡単に分解できます。本体、リコイルスターター、マフラー、キャブレターの構成です。
 エンジンの本体の分解図です。本当は本体のクランクシャフトが通る部分にボールベアリングが圧入さえているのですが外せませんでした。また回転軸(クランクシャフト)は本当は逆側から組み入れるのですが、わかりやすくするために前に配置しました。
エンジンの本体の分解図です。本当は本体のクランクシャフトが通る部分にボールベアリングが圧入さえているのですが外せませんでした。また回転軸(クランクシャフト)は本当は逆側から組み入れるのですが、わかりやすくするために前に配置しました。




 エンジン本体のブロックです。鋳鉄製で実際に近くで見ると表面は少々粗いですが一応エンジンマウントと燃焼室は綺麗に表面加工がされています。右上の写真が燃焼室(シリンダーがおさまる部分)です。左中の写真がエンジンブロックに圧入されているボールベアリングです。クランクケース側にも圧入されています。(右中の写真)左下の写真が排気ポートです。この先にマフラーを取り付けるために綺麗にフライス加工で縁取りさせていますます。
エンジン本体のブロックです。鋳鉄製で実際に近くで見ると表面は少々粗いですが一応エンジンマウントと燃焼室は綺麗に表面加工がされています。右上の写真が燃焼室(シリンダーがおさまる部分)です。左中の写真がエンジンブロックに圧入されているボールベアリングです。クランクケース側にも圧入されています。(右中の写真)左下の写真が排気ポートです。この先にマフラーを取り付けるために綺麗にフライス加工で縁取りさせていますます。





 コンロッドです。
コンロッドです。


 ヘッドです。燃焼室の天井でありというのもあってエンジンでもっとも熱く部分なのでヒートシンクみたいに放熱性が良い構造になっています。この上にちょうどプラグがささります。
ヘッドです。燃焼室の天井でありというのもあってエンジンでもっとも熱く部分なのでヒートシンクみたいに放熱性が良い構造になっています。この上にちょうどプラグがささります。




 クランクケースのふたの部分です。円筒上に出ぱっている方がクランクケース側です。外周の4つのビス穴はリコイルスターターを止める部分で、内側がエンジン本体とこの部品を止めておくためのねじ穴です。右下がガスケットです。
クランクケースのふたの部分です。円筒上に出ぱっている方がクランクケース側です。外周の4つのビス穴はリコイルスターターを止める部分で、内側がエンジン本体とこの部品を止めておくためのねじ穴です。右下がガスケットです。

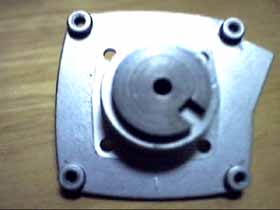








 マフラーの分解図と格部品の詳細です。このエンジンのマフラーは1室構造ですが中、上位モデルは2室構造になっています。長いねじはマフラーの排気管側とエンジンに固定する側を止めるネジで、ちょうど中心を貫通する形になります。排気管の他にある小さな管は排気ガスの圧力を利用して燃料をくみ上げるためにあるもので(バックプレッシャー)、ここと燃料タンクをつなぎます。排気ガスの温度はあまり高くならないので、良く冷却さえしていれば稼動中触っても火傷しませんでした。 決して試さないでください(笑
マフラーの分解図と格部品の詳細です。このエンジンのマフラーは1室構造ですが中、上位モデルは2室構造になっています。長いねじはマフラーの排気管側とエンジンに固定する側を止めるネジで、ちょうど中心を貫通する形になります。排気管の他にある小さな管は排気ガスの圧力を利用して燃料をくみ上げるためにあるもので(バックプレッシャー)、ここと燃料タンクをつなぎます。排気ガスの温度はあまり高くならないので、良く冷却さえしていれば稼動中触っても火傷しませんでした。 決して試さないでください(笑







