
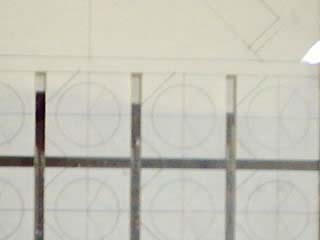
卦書き編
基本的には、罫書き→切り出し→ヤスリがけ→穴あけ→組み立て の順番に作業を進めていきます。
まずはアクリル板の保護紙を剥がさないまま直接その上にシャープペンで卦がいていきます。できるだけ余す部分が少なくまた部品同士の間には切り白を空けておきます。
5mm厚の板なら間隔はだいたい5mmくらいで鋸引きに自信が無い人は+1mm、自信のある人は−1mm位でしょう。
あまり余分に取りすぎても材料の無駄であるしヤスリがけの量が増えてしまいますのでご注意。

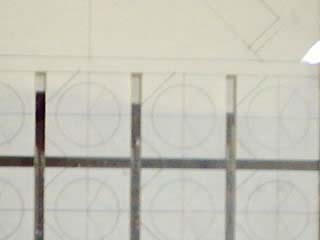
機械で切り出されているような平らな辺に対して垂直に線を引く場合は差し金を以下のように差し金の内側とその平らな辺にあわせると正確に直角が引けます。
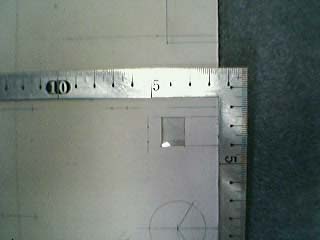
以下のようにこのとき差し金と平らな辺との間に隙間を開けてしまわないように注意。

また差し金が線を書くためのしるしを隠してしまう場合は以下のようにその平らな辺にスケールを当てて差し金に添えてやるといいでしょう。
目で辺と差し金をあわせるよりも正確に簡単に合わせることができます。

シャープペンで卦書き終えたら保護紙を剥がす前に、切り取る線の上をデザインナイフなどでなぞり下のアクリル材に傷をつけます。また穴を開ける場所はポンチを打っておきます。


こういう計測においてプラスチック製品の三角定規はよく使う30°45°60°90°が簡単に書くことが出来て大変便利だが、精度の面から邪道とされてきた。
しかし実際に加工する段階の誤差を考えるとほとんど影響しない程度になってしまう。もちろん工作に手慣れている上級者では差が出てしまうかもしれないが、ねじ穴くらいはキチンと合わせることができるくらいの精度は保証されているはずだ。
卦がく作業にも誤差がある。次々と新たに引いたを線を規準して卦がいていくと線を引くたびにその誤差は蓄積さてれ大きな誤差となる。
しかし規準線(点)から引くのであればその地点からの誤差のみでそれ以上蓄積しない。下の作業を例に取ると同じ長方形でも下の手順の方が誤差が少なくてすむのがわかるでしょう・・・。
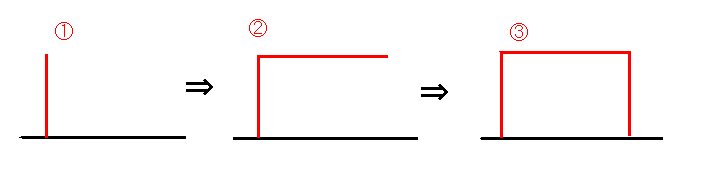
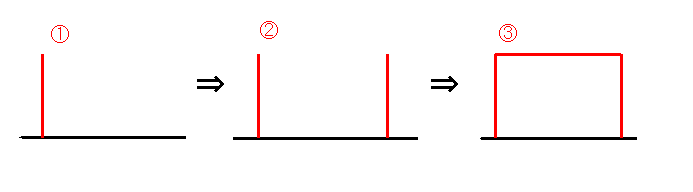
材料に直接卦書きます。もちろんこの場合も切り白を空けて卦書いていきます。長手方向に垂直な線を卦書く場合はL字の内側の角に差し金を沿わして、罫書き線も内側に書くと正確に罫書きやすい。

アングル材の端に書く場合、線を引く位置とL字アングル材の角との距離にスケールが十分入り込める場合は左の写真のようにスケールを内側におく。
右の写真のように狭い場合はスケールを外側に出し、スケールが落ち着かない場合はスケールの下にそのL字アングル材と同じ厚さのものを下敷きにする。

